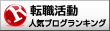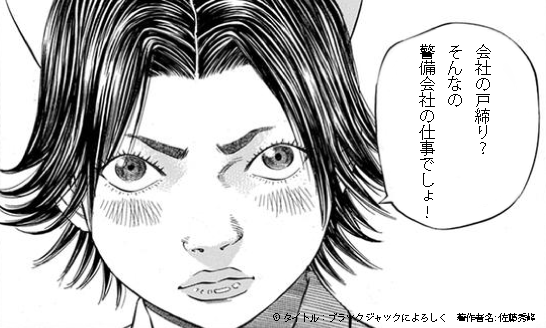仕事を辞めたいと日々悩んでいる皆さん、私の話をちょっと聞いてください。
私が辛い思いをしたその部屋は、薄暗い階段を上った先、小さな電球が仄かに照らす廊下を進んだ右の端にありました。
(何を言っているかわからないと思うので是非、最後まで読み進めてみてください)
普段は一般社員が入ることができない(入る勇気もない)部屋、そこはいつも白いタバコの煙が充満し、中に誰がいるのか、何を話しているのか、想像もできませんでした。
大学時代に記者を目指すものの就職活動に失敗し、先の見えない未来に不安を感じていた私が藁をも掴む思いですがったハローワークの「新聞記者募集」の求人票。
首尾よく潜り込んだ、陸の孤島に位置する地方新聞社は、恐らく半極道の経営陣が幅を利かす巣窟でした。
契約社員として就職したその新聞社は、多くの人が新聞記者と聞いて想像するであろう「社会の悪を暴き、世界に発信し、少しでも暮らしやすい社会の実現のために戦う正義の集団」のイメージを、遥かに凌駕していました。
明日の一面記事を埋めるために草むらに隠れて地域のイザコザを待ち続け、偶然事故の現場に遭遇すれば、困っている地域住民を尻目に助けることなくカメラで撮影。
「俺が獲ったんや、スクープや」と満面の笑顔で原稿を書き起こす。
それは「ペンは剣よりも強し」ともてはやされたジャーナリストの信念の欠片も見えない、エゴの塊がうごめく現場でした。
これが、憧れのジャーナリストなのか。
社内で印刷業務も兼ねていたその新聞社は、むしろ記者よりも印刷従事者を探していたのかもしれません。
私の記者としての修行は午前中でさっさと終わりとなり、午後には印刷スタッフに鞍替え。
印刷した新聞を車に詰めたら「記者は動いてなんぼや」とどやされ、新聞配達に出発。
通いつめた新聞販売所の担当者には「毎日印刷、ご苦労様」とお茶をいただく始末。
これが、憧れのジャーナリストなのか。
もちろん、記者としては完全なる素人である自分がいきなり、記者として独り立ちできるほど世の中甘くないのは知っていました。
深夜まで先輩記者のスナック通いのために大型バンを運転し、「たらふく飲んだ次の日に運転できたらほんまもんの記者やで」と言われて日本酒を入れたり、リバースしてしまったり。
社宅という名の会社の支社(畳張りのほぼ宴会場)の部屋で寝ていると、深夜に鍵のない扉が開いてどんちゃん騒ぎが始まったり。
明らかに常軌を逸した現状に薄々違和感を感じ始めていましたが「これも、将来記者として活躍するためだ」と必死に自分に言い聞かせ、不眠気味の重い体を奮い立たせながら戦い続けていました。
私が、会社を辞めようと思った瞬間。
この記事のテーマを見たとき、最初は私の中で答えを出すことがどうしても出来ませんでした。
睡眠不足で全く頭が回らない状態で無修正のアダルトビデオを鑑賞させられ「抜かんかい」と言われた時か。
いや、その新聞社主催の地域のお祭りにスタッフとして駆り出された際に、会場を冷やすために運んできたトラック一杯の氷を、社内スタッフが必死の形相で一斉に蹴り壊し続ける異様な光景を見た時か。
編集長という役職を与えられた初老の新聞記者が、社長の思いつきの一言で大事な一面の記事の真相を捻じ曲げた姿を見た時か。
色々と思いを巡らせてみましたが、それらは全て決定打になっていない気がしました。
何が、私にあの新聞社を辞めようと決断させたのか。
考え続けていたある瞬間、不意に一つのシーンが私の頭の中をかすめました。
あれだ、右の端の部屋に入った時だ。
普段は一般社員が入ることができない(入る勇気もない)部屋、そこはいつも白いタバコの煙が充満し、中に誰がいるのか、何を話しているのか、想像もできませんでした。
ただ、その入り口の扉の上には「社長室」と書かれた薄汚れた木の板が掲げられており、社内の編集、広告、営業部それぞれの幹部がいつも気だるく出入りしている空間だというのは、週末の大掃除の時に感づいていました。
「ちょっと来いや」。
普段の取材時にはいつも温和な笑顔を浮かべる編集部の幹部(編集長ではない)が、後ろからいきなり私を小突きました。
「社長室、来いや」。
取材でいつも外に出ている割にいつも青白い顔が印象的なその幹部が、のそりのそりと歩きながら、私を社長室へと先導して行きます。
編集室の他の記者達が、横目でこちらを見遣っているのが分かりました。
何の取材もしていない新米記者が、階段を上った、右の端の部屋に呼び出されている。
それは、どう考えても不可解な状況でした。
褒められる、のではないだろう。
社会人となって日も浅い私でも、それくらいは想像できました。
その部屋を開けると、案の定、白いタバコの煙が充満していました。
部屋の中には、編集と広告、営業の幹部がタバコをふかし、我が社のインク臭い朝刊を見るともなく開きながら、部屋の両脇にある薄汚れたソファに踏ん反り返っています。
部屋の奥には、新聞を丸めて机を叩く丸刈がトレードマークの社長の姿。
褒められるのではない、その時に私は確信しました。
「そんなこわい顔すんなや、こっち来いや、おい」目が笑っていない社長に呼ばれ、部屋の奥へと進みました。
「毎日、頑張っとるみたいやないか。話はみんな、聞いとるわ」。
社長の野太い声が、部屋中に響いています。
「なあ、そうやんな」幹部連中はしきりに頷いています。
褒められるのか、そう思った矢先です。
「何や、その目は。何、睨みきかしとんじゃ、お前」。
別に睨んでいません、声にはしませんが。
「せやけど、何かな、うちの可愛い部下が、嫌いなんやって。お前」。
踏ん反り返る幹部を、社長が見遣っています。
「何や、気に食わんのやって。お前」。
何も記者として仕事らしい仕事をしていない私の、何が気に食わないと言うのでしょう。
聞きたいですが、声になりません。
「はあ・・すみません」。
「なめとんのか、なあ」「いえ」「なめとるやろ、てめえ」「いえ」。
タバコの煙が目に入り、涙が出てきます。
「泣いても知らんぞ、お前。俺の可愛い部下、馬鹿にしとるんとちゃうんか、おい」「・・」「どないするんや、殴るぞ、なんか言えや、オラ」。
タバコの煙ではない、本当の恐怖からの涙があふれてきました。
「殴るぞ、おい」「殴るぞ、マジで」。
部屋にいた幹部は半笑いでした。
ここにいたら、本当に殴られる、本当に殺される。
せっかく掴んだ記者の仕事を、手放そうと覚悟したのは、間違いなく、その瞬間。
白いタバコの煙が充満する、だだっ広い部屋の中の出来事がきっかけでした。
現在はその新聞社のある県から遥か遠くに引っ越し、新天地にて言葉に関わる仕事をしている私ですが、不意にあの新聞社で出逢った修羅場と地獄を思い出します。
今の職場でも、毎日のように思うようにいかない事態に遭遇し、弱ってしまう事が多々あります。
もちろん会社を辞めたいとさえ思うことも。
そんな時に、折れてしまいそうな私の心を力強く支えてくれるのは何故か、あの階段を登り、右の端にあった部屋の記憶なのです。
駄目だ、苦しい、逃げてしまうか。
でも、あの本物の地獄の中から勇気を出して逃げ出した、乗り切った自分なら、もしかしたらこんな問題、何とか解決できるのでないか。
そうやって、弱い心を奮い立たせようとする自分がいるのです。
今、目の前の壁に押し潰されそうになって、もがき苦しんでいる人が世界中にどれだけいるのでしょうか。
そんな方々に向かって「頑張れ、逃げるな」と偉そうに励ますことは、私にはできません。
私も一度は逃げるように会社を辞めた人間ですから。
でも、その苦しみ、涙を流した鮮烈な記憶は、きっと未来で貴方を救ってくれるはずです。
私の小さな、一生忘れることのないであろう記憶の断片を読んで「あ、まだ俺マシかも」「私は、この人に比べれば」とホッと、胸をなで下ろす方がいてくだされば幸いです。